僧侶×行政書士による墓じまいの解説

この記事は薬師行政書士事務所による記事を双林寺ブログ向けに改編したものです。
元記事https://yakushi-gyosei.com/2025/08/18/hakajimai-kaisou/
こんにちは。双林寺副住職兼薬師行政書士事務所の本間英純です。 「お墓を継ぐ人がいない」「遠方でお参りが難しい」などの理由から、墓じまい(改葬)を検討される方が増えています。 ただし、墓じまいは役所への申請と宗教儀礼、霊園や墓地のあるお寺とのやり取り、そして石材店の手配等が絡むため、正しい手順を踏むことが大切です。 行政手続と寺院実務の両面を見てきた行政書士×僧侶の視点から、分かりやすく手順を解説します。
- 墓じまいの基本的な流れ(9ステップ)
- 行政書士&僧侶に依頼するメリット
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
墓じまいの基本的な流れ(9ステップ)
1. 家族・親族との相談
まずは親族間でしっかり合意形成を行います。後から反対が出ると、手続きが止まることがあります。現在の墓地管理者(菩提寺・霊園)にも早めに意向を伝えましょう。双林寺墓地の場合は住職まで。
2. 改葬先の決定
改葬先が決まらないと、役所の申請ができません。主な選択肢は以下です。
- 新しい墓地・霊園
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 樹木葬
- 手元供養(自宅にお骨を置く)
- 散骨(粉末にしたお骨を海に撒く海洋散骨など)
3. 改葬承諾書の取得(改葬先から)
改葬先の管理者から改葬の承諾を得、改葬承諾書に署名を貰う。
4. 埋葬証明書の取得(現在の墓地から)
現在の墓地管理者から埋葬証明書を発行してもらいます。檀家としての精算(閉眼供養、墓石の撤去、区画整備等)が必要となる場合があります。
5. 改葬許可申請(市区町村役場)
現在の墓地がある市区町村役場に申請します。一般に必要となる書類は次のとおりです。
- 改葬許可申請書
- 改葬承諾書
- 埋葬証明書
審査後、改葬許可証が交付されます。
6. 閉眼供養(魂抜き)
必要に応じて遺骨の取り出し前に、僧侶による閉眼供養を行います。これにより墓石や納骨室を撤去・移転できる状態に整えます。 閉眼供養は強制ではありません。しかしながら住職や石材店から行うように言われた場合は従った方がスムーズに進むと思います。
7. 遺骨の取り出し・運搬
石材店や専門業者に依頼し、墓石の解体および遺骨の取り出しを行います。改葬先へ移送する際は改葬許可証を携行します。
8. 新しい墓地での納骨・開眼供養
改葬先で改葬許可証を提出し、納骨します。必要に応じて開眼供養(魂入れ)を行います。
9. 墓所の原状回復
旧墓所は石材を撤去し、更地にして返還します。具体的な方法や費用は管理規約によって異なります。注意:手続や必要書類の名称・様式・費用感は自治体・管理者ごとに異なります。必ず該当自治体・管理者の最新ルールをご確認ください。
行政書士に依頼するメリット
改葬許可申請や関連書類の作成・代理提出により、手続の負担を軽減できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 期間はどれくらいかかりますか?
親族間の同意形成や改葬先の選定期間を含めると、自治体や管理者の対応速度によって幅があります。申請~許可までの期間も自治体差があるため、余裕をもった計画が安心です。
Q. 費用の目安はありますか?
役所の手数料に加え、石材店の解体・撤去費用、運搬費用、寺院へのお布施・離檀に伴う費用などが生じます。墓所の規模、立地、管理規約により大きく変動します。
Q. 離檀料は払わなければいけないですか?
墓地使用契約・管理規約・内部規程に「離檀時の費用」等の根拠がある場合を除いて支払いに法的義務はありません。中には高額な離檀料を請求された、という話を耳にします。その場合はその宗派の包括団体(曹洞宗の場合は宗務庁)に確認することをお勧めします。 しかしながら、長年お世話になった感謝として普段の法事のお布施と同額程度をお渡しする事が多いようです。 因みに双林寺では、離檀料を頂いておりません。
Q. 親族間で意見が割れています。
後日の紛争回避のため、合意形成の過程を丁寧に進めましょう。第三者の専門家が手順と費用・スケジュールを可視化することで、話し合いが前進することがあります。
まとめ
墓じまいは、改葬先の確定 → 証明書の取得 → 改葬許可 → 供養 → 解体・運搬 → 納骨 → 原状回復という流れで進みます。場合によって順番は前後する場合もございます。 自治体・管理者で細部が異なるため、最新のルールを確認しつつ、専門家のサポートを活用すると安心です。
※本記事は一般的な解説です。実際の手続・必要書類・費用は自治体・墓地管理者・個別事情により異なります。
薬師行政書士事務所 双林寺副住職 本間英純
987-2264
宮城県栗原市築館薬師台1-1
携帯 080-7845-6401
TEL 0228‐22‐5028
E-mail:yakushigyousei.2022@gmail.com
問い合わせの際はホームページのブログを見たとお伝えください。
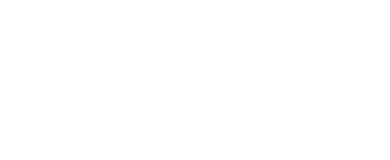









この記事へのコメントはありません。